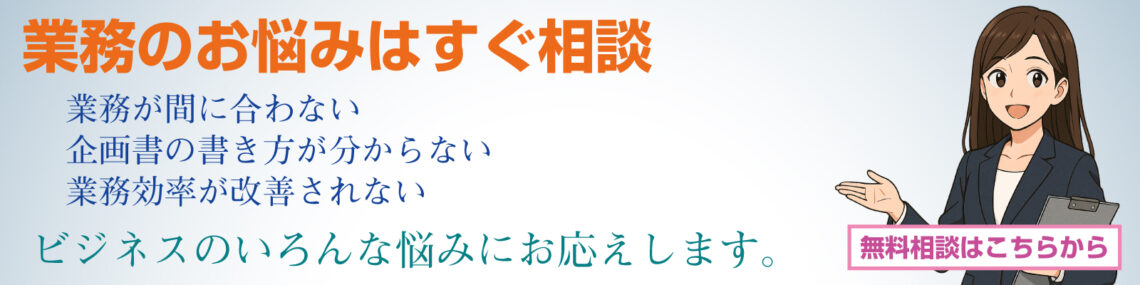仕様が決まっていない場合の企画書の仕様
企画書の仕様は、細かく決められている場合もあれば、何も決まっていない場合もあります。中には様式を使って書くよう求められる場合もあります。
基本的には指定の様式に従えば良いのですが、中には「暗黙の了解」というものもあります。企画書を提出しても、後からやり直しという場合もありますので、基本的なルールは守るようにしましょう。
文字のサイズとフォントについて
官公庁はほぼmicrosoftのアプリケーションを採用しています。最近はだいぶんなくなりましたが、Windows 10を使っているところやOffice2013を使っているところもないとは言えません。なので、フォントはメイリオ、游ゴシック、游明朝のいずれかに統一するのが無難です。他のフォントを使って、仮に担当者のPCの中にそのフォントが入っていなかったら、レイアウトが崩れて企画書の内容が読めなくなる可能性もあります。
サイズは10ポイント以上にしましょう。経験上、画像のキャプションや表の文字は9ポイントまでなら大丈夫でした。小さな文字は読めないと指摘が入る場合があります。
画像のサイズと解像度について
画像は小さすぎると見えないので、せめて3cm以上にしましょう。表など、文字が入る場合は、周りの文字の大きさに合わせて読める程度の画像サイズにしておきます。解像度については、これくらいの大きさならスマートフォンで撮影したものでも十分に通じます。
画像の著作権について
企画書の著作権は委託者、つまり官公庁が持つことになります。企画書は基本的に公表されるものではありませんが、著作権侵害があった場合、相当な信用低下につながるので、必ず提供元が明らかで、商用に使える画像を使うようにしてください。
ページの向きとサイズ
ほとんどの仕様は、A4縦、横書きです。左側にホッチキス留めで下にページ番号を付けます。そのため、横幅はおおむね17㎝程度にしておきましょう。A4サイズの横幅は21cmですから、だいたい左右に2cm程度の空きができます。
ページ数について
ページ数に規定がない場合は何ページでも書いていいのですが、できるだけページ数は減らすようにしてください。企画書を評価するのは複数人ですが、ページ数が多いと、それだけでうんざりするので気持ち的にちゃんと読んでくれない可能性があります。そして、その分1ページの中にできるだ内容を詰め込んでください。読む人のことを考えるのは企画書を作るうえで大事なところです。