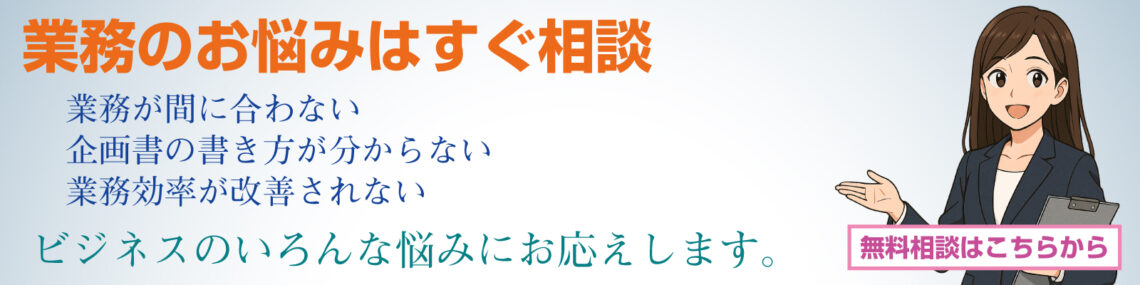九州大学うみつなぎでは、定期的に海の現地教室である「海辺の教室」を開催しています。当社も活動のサポートを通して、さまざまな学びの場を提供しています。
泉川の干拓
糸島市の泉川は、もとは大きな入江でした。16世紀末頃から干拓を始め、約250年で400町以上の田畑ができました。今回のツアーは、糸島の地形的な解説と、干拓事業の跡地を歩いてたどりました。
イベントについて
釜塚古墳・伊都国宮地嶽神社
釜塚古墳は5世紀に建設された北部九州最大級の円墳です。九州はもともと甕棺による埋葬が一般的でしたが、大和王権の影響で古墳が築かれるようになりました。釜塚古墳は伊都国が大きな勢力として九州北部の交易を担っていたことがうかがえます。
伊都国宮地嶽神社は吉備真備の出征に際して宗像郡から勧請したとされています。近くの神在神社が熊野神社系列であることを含めると、地域の支配者がさまざまと入れ替わったのかもしれません。いずれにせよ、この地域が重要な交易の拠点であることがわかります。
仙厓歌碑
千早新田が干拓されたあと、聖福寺の仙厓和尚が詠んだ歌が刻まれています。聖福寺は福岡市博多区にある臨済宗の禅寺です。臨済宗の開祖である栄西が建立した日本最初の本格的な禅宗寺院としても有名です。
今津には勝福寺や寿福寺といった臨済宗の寺院があり、鎌倉時代の今津周辺が臨済宗の影響が強かった時期があります。
千早新田の干拓記念と聖福寺の和尚の関係性は興味深いところです。
千早新田石垣跡
江戸時代の干拓は、初期は浅瀬に土砂を埋める者でしたが、後期になると、引き潮のときに周りを土嚢と石垣で囲う方法が採られるようになりました。このような方法は現在でも干拓事業で採用されているもので、その先駆けとして今に残る文化財と言えます。
ツアーでは、このようなポイントを巡り、泉川周辺の歴史を体験するものです。