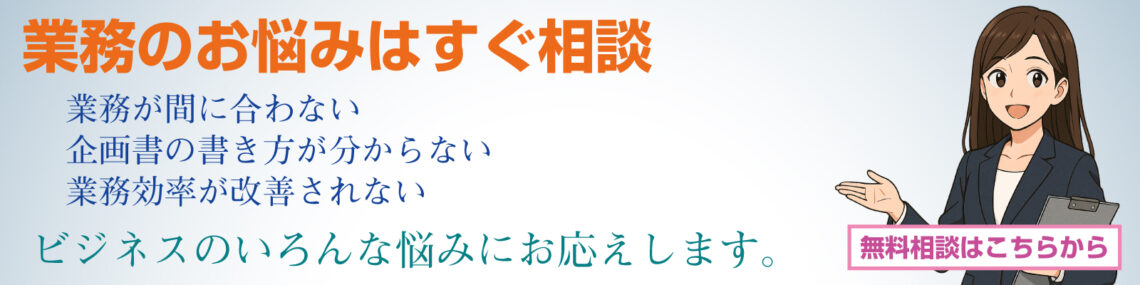九州大学うみつなぎでは、定期的に海の現地教室である「海辺の教室」を開催しています。当社も活動のサポートを通して、さまざまな学びの場となっています。
泉川のハマボウとは
糸島市の西岸は「泉川」という川が流れています。元は入江でしたが、黒田長政の時代に菅正利が開発を行い、官位の和泉守から和泉川と名付けられたと言われています。
この和泉川の淡水と海水の境にある場所にハマボウが植生されています。他の場所は海藻や陸の植物に負けるため、群生できないそうです。このような場所は護岸工事によって失われ、現在ハマボウは絶滅危惧種にも指定されています。
泉川のハマボウは「泉川ハマボウの会」の環境美化等の活動により保全されていて、夏の季節はきれいな黄色の花を咲かせています。
イベントについて
イベントは大石公民館をお借りして実施しました。公民館の管理をされている島崎氏に大石の郷土史を伺い、実際にハマボウの観察会を行いました。
大石という地名は、可也山から切り出した石を保存しておいたことにより付いた地名で、ここに集積された石は神社や石垣などに使われていたそうです。有名なのは、日光東照宮の一の鳥居で、ここから泉川を出て、瀬戸内海を通り、太平洋経由で江戸、日光まで運ばれたそうです。当時の土木技術の高さがうかがえる事例です。
また、この地域は昭和18年に軍によって買い上げられ、一時飛行訓練場となっていました。その石碑は現在でも残っています。